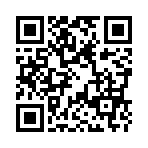2023年02月12日
蔵めぐり「奄美大島開運酒造」
日頃お世話になっている黒糖焼酎「れんと」を造っている「奄美大島開運酒造」さんに蔵の事や
黒糖焼酎の事、いろいろ話を伺ってきました。

1996年創業と奄美の蔵の中では最後発である奄美大島開運酒造(以下 開運酒造)は、
前身の名瀬にあった戸田酒造から事業を引き継ぐ形で黒糖焼酎造りを始めます。
その後蔵の想いである「食と養生の郷」を実現するために、創業者の故郷である奄美大島の
宇検村に蔵を移し黒糖焼酎造りを開始。現在に至ります。創業当時は何もわからないゼロからの
スタートで商品開発、製造、販売と大変な苦労が有ったそうですが、蔵の挑戦する心に対し
官民から沢山支援があり徐々に黒糖焼酎蔵として体を成していきます。
そしてこの時当時まだ新しかった技術である減圧蒸留と音響熟成を取り入れた黒糖焼酎
「れんと」を発売し島内外で沢山の支持を獲得します。

写真は音響熟成中のれんと
『世界が認めた自然環境。』
開運酒造を蔵見学で訪れた際に杜氏長である高妻さんが蔵の入口で迎えてくださり
「先ずは蔵周辺の自然を見てください」と挨拶も手短に車で湯湾岳一帯を案内してくれました。

蔵の周囲には自然豊かな奄美大島でもひと際緑が蔽い茂る湯湾岳の大自然が広がっており、
2021年に決まった世界自然遺産登録において奄美エリアはこの湯湾岳一帯が中心地に指定
されおり、標高694.4メートルの湯湾岳は奄美大島の最高峰の山で古くから奄美の人達の
山岳信仰の対象となっている霊峰だ。

年間に2000mm降ると言われる豊富な雨は一旦、湯湾岳へ染み込み地層で濾過されながら
美味しい地下水となって地表へ再び湧き出る。
そして、「この地層で濾過された水が美味しい黒糖焼酎を造るのに欠かせないのだ。」
と高妻さんは言う。
現在、代表銘柄の「れんと」をはじめ開運酒造のお酒はすべてこの湯湾岳の雄大な自然から
湧き出た水を使用しており、同蔵はこの水でお酒を造る奄美で唯一の酒蔵との事だ。

『想いも一緒にお酒に込める。』
クリーンで真新しい蔵の一角に昔ながらの人の手で麹を攪拌する三角棚が有る。
「蔵の機械化が進んでも、酒造りの中で杜氏が実際に原料を触り、その重さを感じる工程は
入れておく」との考えから蔵では人手がかかる三角棚をあえて取り入れているそうだ。
杜氏が原料を触り重さを知る事で、その工程で造り手の想いや真心まで一緒にお酒に込める。
全部の工程を機械でやってしまうと、お酒が無機質な物になってしまう。人が飲むからこそ、
人のぬくもりが感じられるお酒を造りたいとの思いがあるのだそうです。

ふだん何気なく飲んでいる開運酒造の黒糖焼酎にそんな思いが込められていたとは正直この
時まで全く知りませんでした。次回から「れんと」を飲むときはそういったことも感じながら
飲んでみたいと感じたお話でした。
(株)奄美大島開運酒造
〒894-3301 鹿児島県大島郡宇検村湯湾2924−2
※蔵見学には事前予約が必要です。
蔵見学申し込みフォーム
*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚
【有限会社リカーショップメグミ】
●営業時間
月~土 11:00~24:00
日曜日 17:00~24:00
●住所
鹿児島県奄美市名瀬金久町15-4
●電話番号
0997-52-1327
●2000円以上お買い求めいただきましたら無料で配達いたします。
【配達エリア】
金久町・柳町・矢之脇町・入舟町・港町・
幸町・末広町・塩浜町・長浜町・永田町・井根町・石橋町・久里町
【配達時間】
14:00~21:00
●インターネットでのご購入はこちら↓
☆楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/noni-o-f/
☆Yahooショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/amaminomegumi/
黒糖焼酎の事、いろいろ話を伺ってきました。

1996年創業と奄美の蔵の中では最後発である奄美大島開運酒造(以下 開運酒造)は、
前身の名瀬にあった戸田酒造から事業を引き継ぐ形で黒糖焼酎造りを始めます。
その後蔵の想いである「食と養生の郷」を実現するために、創業者の故郷である奄美大島の
宇検村に蔵を移し黒糖焼酎造りを開始。現在に至ります。創業当時は何もわからないゼロからの
スタートで商品開発、製造、販売と大変な苦労が有ったそうですが、蔵の挑戦する心に対し
官民から沢山支援があり徐々に黒糖焼酎蔵として体を成していきます。
そしてこの時当時まだ新しかった技術である減圧蒸留と音響熟成を取り入れた黒糖焼酎
「れんと」を発売し島内外で沢山の支持を獲得します。

写真は音響熟成中のれんと
『世界が認めた自然環境。』
開運酒造を蔵見学で訪れた際に杜氏長である高妻さんが蔵の入口で迎えてくださり
「先ずは蔵周辺の自然を見てください」と挨拶も手短に車で湯湾岳一帯を案内してくれました。

蔵の周囲には自然豊かな奄美大島でもひと際緑が蔽い茂る湯湾岳の大自然が広がっており、
2021年に決まった世界自然遺産登録において奄美エリアはこの湯湾岳一帯が中心地に指定
されおり、標高694.4メートルの湯湾岳は奄美大島の最高峰の山で古くから奄美の人達の
山岳信仰の対象となっている霊峰だ。

年間に2000mm降ると言われる豊富な雨は一旦、湯湾岳へ染み込み地層で濾過されながら
美味しい地下水となって地表へ再び湧き出る。
そして、「この地層で濾過された水が美味しい黒糖焼酎を造るのに欠かせないのだ。」
と高妻さんは言う。
現在、代表銘柄の「れんと」をはじめ開運酒造のお酒はすべてこの湯湾岳の雄大な自然から
湧き出た水を使用しており、同蔵はこの水でお酒を造る奄美で唯一の酒蔵との事だ。

『想いも一緒にお酒に込める。』
クリーンで真新しい蔵の一角に昔ながらの人の手で麹を攪拌する三角棚が有る。
「蔵の機械化が進んでも、酒造りの中で杜氏が実際に原料を触り、その重さを感じる工程は
入れておく」との考えから蔵では人手がかかる三角棚をあえて取り入れているそうだ。
杜氏が原料を触り重さを知る事で、その工程で造り手の想いや真心まで一緒にお酒に込める。
全部の工程を機械でやってしまうと、お酒が無機質な物になってしまう。人が飲むからこそ、
人のぬくもりが感じられるお酒を造りたいとの思いがあるのだそうです。

ふだん何気なく飲んでいる開運酒造の黒糖焼酎にそんな思いが込められていたとは正直この
時まで全く知りませんでした。次回から「れんと」を飲むときはそういったことも感じながら
飲んでみたいと感じたお話でした。
(株)奄美大島開運酒造
〒894-3301 鹿児島県大島郡宇検村湯湾2924−2
※蔵見学には事前予約が必要です。
蔵見学申し込みフォーム
*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚
【有限会社リカーショップメグミ】
●営業時間
月~土 11:00~24:00
日曜日 17:00~24:00
●住所
鹿児島県奄美市名瀬金久町15-4
●電話番号
0997-52-1327
●2000円以上お買い求めいただきましたら無料で配達いたします。
【配達エリア】
金久町・柳町・矢之脇町・入舟町・港町・
幸町・末広町・塩浜町・長浜町・永田町・井根町・石橋町・久里町
【配達時間】
14:00~21:00
●インターネットでのご購入はこちら↓
☆楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/noni-o-f/
☆Yahooショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/amaminomegumi/
2019年01月28日
蔵見学-富田酒造-
先日、家の近くにある富田酒造に蔵見学に行ってきました!

奄美黒糖焼酎『龍宮』でお馴染みの富田酒造は、奄美がまだアメリカの統治下だった
昭和26年の今から68年前に初代の富田豊重(とよしげ)氏によって創設されました。
富田酒造の蔵としての特徴は、今では珍しい1次、2次と全て甕を使って仕込む
全量甕仕込みとその甕仕込みと相性が良い麹とされている黒麹を使った焼酎造りです。

うるち米を仕込んで出来る1次仕込み中の酒母

黒糖が加わった2次仕込み中のもろみ
原料に対しての拘り
米
富田酒造で一次仕込みで使用しているお米は国産のうるち米で、これを全自動の製麹機で
混ぜながら麹菌を散布するそうですが、うるち米は一般的によく使われているタイ米等と比べて
粘り気があるため混ぜている途中ダマになりやすく、
機械を何度か止めて手でお米を解さないといけない為
タイ米を使用した場合と比べて手間がかかるのだそうです。
それでも国産うるち米に拘るのは、焼酎として出来上がった時の香りが格段に良いからと言います。
お米に対しての拘りは、お米と黒糖の使う比率でも分かります。
富田酒造でははお米1に対して黒糖を約1.25程の割合で仕込むんだそうです
このお米の割合は、ほかの蔵と比べて高いそうです。
黒糖
『らんかん』、『かめ仕込み』、『龍宮』に
使われる黒糖は、沖縄群島の様々な島から仕入れられます。
『まーらん舟』は徳之島産の黒糖を使用しています。
それぞれの島の風土などの違いが黒糖の味に出て、それが
各銘柄の個性になるそうです。

例えば
沖縄群島の波照間島や多良間島等の黒糖は、島に雨が少ないので塩のほろ苦さが出て、
酒質はキリッと潮風を感じる味わいになり
雨が多い徳之島産の黒糖は柔らかく上品な甘さがあって。酒質はトローっと上品な
旨味を感じる味わいになります。


蒸気を利用して黒糖を溶かすための専用の釜
周りに釜全体を囲むようにジャケット(配管)があって、そこに5度の冷水を通し
溶した黒糖を急速に冷却。そうする事で黒糖の香りが飛ばない様にします。
焼酎にキレを生み出す蒸留器
富田酒造さんに置いてある蒸留器の特徴は2つのタンクを置いてある位置に
高低差をつけていて、この2つを結んでいるスワンネックと言われる管が長い事です。

下のタンクで暖められたもろみのアルコール分は90度ほどで気化し管を
通って上のタンクに移動するのですが、管が長い為に途中温度差が生じ
一度液体に戻ってまた下のタンクに落ちるそうです。この工程で焼酎の味に
キレを生み出す効果が有るそうです。
しかしこの工程もあまりやり過ぎると面白みのない味わいに成ってしまう事から、
管の途中に防温材の様なものを巻き付けてその時の外気温なども考慮して
味を調整して行くんだそうです。
今回、今まで分からなかった事等を、色々質問させて頂き
その一つ一つに本当に丁寧に答えて頂きました!
富田さん!貴重なお時間をありがとうございました!

奄美黒糖焼酎『龍宮』でお馴染みの富田酒造は、奄美がまだアメリカの統治下だった
昭和26年の今から68年前に初代の富田豊重(とよしげ)氏によって創設されました。
富田酒造の蔵としての特徴は、今では珍しい1次、2次と全て甕を使って仕込む
全量甕仕込みとその甕仕込みと相性が良い麹とされている黒麹を使った焼酎造りです。

うるち米を仕込んで出来る1次仕込み中の酒母

黒糖が加わった2次仕込み中のもろみ
原料に対しての拘り
米
富田酒造で一次仕込みで使用しているお米は国産のうるち米で、これを全自動の製麹機で
混ぜながら麹菌を散布するそうですが、うるち米は一般的によく使われているタイ米等と比べて
粘り気があるため混ぜている途中ダマになりやすく、
機械を何度か止めて手でお米を解さないといけない為
タイ米を使用した場合と比べて手間がかかるのだそうです。
それでも国産うるち米に拘るのは、焼酎として出来上がった時の香りが格段に良いからと言います。
お米に対しての拘りは、お米と黒糖の使う比率でも分かります。
富田酒造でははお米1に対して黒糖を約1.25程の割合で仕込むんだそうです
このお米の割合は、ほかの蔵と比べて高いそうです。
黒糖
『らんかん』、『かめ仕込み』、『龍宮』に
使われる黒糖は、沖縄群島の様々な島から仕入れられます。
『まーらん舟』は徳之島産の黒糖を使用しています。
それぞれの島の風土などの違いが黒糖の味に出て、それが
各銘柄の個性になるそうです。

例えば
沖縄群島の波照間島や多良間島等の黒糖は、島に雨が少ないので塩のほろ苦さが出て、
酒質はキリッと潮風を感じる味わいになり
雨が多い徳之島産の黒糖は柔らかく上品な甘さがあって。酒質はトローっと上品な
旨味を感じる味わいになります。


蒸気を利用して黒糖を溶かすための専用の釜
周りに釜全体を囲むようにジャケット(配管)があって、そこに5度の冷水を通し
溶した黒糖を急速に冷却。そうする事で黒糖の香りが飛ばない様にします。
焼酎にキレを生み出す蒸留器
富田酒造さんに置いてある蒸留器の特徴は2つのタンクを置いてある位置に
高低差をつけていて、この2つを結んでいるスワンネックと言われる管が長い事です。

下のタンクで暖められたもろみのアルコール分は90度ほどで気化し管を
通って上のタンクに移動するのですが、管が長い為に途中温度差が生じ
一度液体に戻ってまた下のタンクに落ちるそうです。この工程で焼酎の味に
キレを生み出す効果が有るそうです。
しかしこの工程もあまりやり過ぎると面白みのない味わいに成ってしまう事から、
管の途中に防温材の様なものを巻き付けてその時の外気温なども考慮して
味を調整して行くんだそうです。
今回、今まで分からなかった事等を、色々質問させて頂き
その一つ一つに本当に丁寧に答えて頂きました!
富田さん!貴重なお時間をありがとうございました!
2018年12月31日
蔵見学-西平本家-
この前西平本家さんに蔵見学の為にお邪魔しました。
※写真は他のサイトから引用しました

蔵見学をしに来たと言う事を伝えると、忙しいと思われる中わざわざ
人員を割いて色々説明して頂きました。感謝です。
始めにモニターの在る部屋で会社の歴史や、奄美に黒糖焼酎が伝わった背景など、
スライド写真を交えて丁寧に説明を頂き、その後は実際に工場の中を案内してもらいました。
西平本家の創業は大正14年で創業当時は喜界島で泡盛を造っていたそうです。
その後昭和2年に名瀬市(現奄美市)の今の場所に移転し現在に至るそうです。

創業時に使用していた看板
『特徴』
西平本家の焼酎の特徴は国産原料への拘りと、独自の伝統製法です。
仕込みの段階でかなり手間が掛かる『半麹三段仕込』と言う独自の製法
により、麹の糖化がゆっくり進み結果、味がまろやかになるんだそうです。
『一次~二次仕込』

この機械で洗米した後にお米を蒸して麹菌を吹き付け発酵を促します。

この機械で米を寝かせて発酵を促します。

一次、二次仕込は此方の昔ながらの瓶を使います
発酵させた一次麹に酒母と水を加えて瓶の中で更に発酵
※写真は他のサイトから引用しました


発酵中は瓶の中の温度が上がりすぎてしまうのでこの中に水を通してもろみの温度を
調節するんだそうです。
一次仕込、二次仕込は10日から11日ぐらい掛かるそうですが
今は仕込みのシーズンではないと言う事で、瓶には何も入っていませんでした。
『三次仕込』

此方のタンクで黒糖のブロックを溶かします。ブロックは一つ30キロも有るそうです。

一次もろみと黒糖液を混ぜ合わせて二次もろみをこのタンクで仕込みます。
出来上がった2次もろみを蒸留させます。
『蒸留』

西平本家さん独自の単式蒸留器可変式三方弁と言われる特殊な蒸留器で蒸留。
3つの管を通るそれぞれ質の異なる酒質組み合わせでタイプの異なる銘柄のお酒を
造るんだそうです。
因みに最初に出てくる『初垂れ』と言われる原酒はアルコール度数が70度だそうです。
たぶん火が付きます。
『最後に』
仕込みの作業はとても大変かつ同時に黒糖焼酎の味を左右するとても重要な工程
だそうで杜氏の方は泊り込みでもろみの世話をするんだそうです。
また杜氏の性格がお酒の味に出るそうで、せっかちな人が
仕込むとせっかちな味に成り、のんびりした人が仕込むとのんびりした味に
成ると言う話が印象的でした。

お得な情報も配信 『めぐみ通信@LINE』 も宜しくお願いします!

(有)ピーシーショップめぐみ
TEL 52-1327
駐車場 あり
営業時間 10:00-24:00
休み お盆、元日のみ
※写真は他のサイトから引用しました

蔵見学をしに来たと言う事を伝えると、忙しいと思われる中わざわざ
人員を割いて色々説明して頂きました。感謝です。
始めにモニターの在る部屋で会社の歴史や、奄美に黒糖焼酎が伝わった背景など、
スライド写真を交えて丁寧に説明を頂き、その後は実際に工場の中を案内してもらいました。
西平本家の創業は大正14年で創業当時は喜界島で泡盛を造っていたそうです。
その後昭和2年に名瀬市(現奄美市)の今の場所に移転し現在に至るそうです。

創業時に使用していた看板
『特徴』
西平本家の焼酎の特徴は国産原料への拘りと、独自の伝統製法です。
仕込みの段階でかなり手間が掛かる『半麹三段仕込』と言う独自の製法
により、麹の糖化がゆっくり進み結果、味がまろやかになるんだそうです。
『一次~二次仕込』

この機械で洗米した後にお米を蒸して麹菌を吹き付け発酵を促します。

この機械で米を寝かせて発酵を促します。

一次、二次仕込は此方の昔ながらの瓶を使います
発酵させた一次麹に酒母と水を加えて瓶の中で更に発酵
※写真は他のサイトから引用しました


発酵中は瓶の中の温度が上がりすぎてしまうのでこの中に水を通してもろみの温度を
調節するんだそうです。
一次仕込、二次仕込は10日から11日ぐらい掛かるそうですが
今は仕込みのシーズンではないと言う事で、瓶には何も入っていませんでした。
『三次仕込』

此方のタンクで黒糖のブロックを溶かします。ブロックは一つ30キロも有るそうです。

一次もろみと黒糖液を混ぜ合わせて二次もろみをこのタンクで仕込みます。
出来上がった2次もろみを蒸留させます。
『蒸留』

西平本家さん独自の単式蒸留器可変式三方弁と言われる特殊な蒸留器で蒸留。
3つの管を通るそれぞれ質の異なる酒質組み合わせでタイプの異なる銘柄のお酒を
造るんだそうです。
因みに最初に出てくる『初垂れ』と言われる原酒はアルコール度数が70度だそうです。
たぶん火が付きます。
『最後に』
仕込みの作業はとても大変かつ同時に黒糖焼酎の味を左右するとても重要な工程
だそうで杜氏の方は泊り込みでもろみの世話をするんだそうです。
また杜氏の性格がお酒の味に出るそうで、せっかちな人が
仕込むとせっかちな味に成り、のんびりした人が仕込むとのんびりした味に
成ると言う話が印象的でした。

お得な情報も配信 『めぐみ通信@LINE』 も宜しくお願いします!

(有)ピーシーショップめぐみ
TEL 52-1327
駐車場 あり
営業時間 10:00-24:00
休み お盆、元日のみ
2018年05月20日
蔵見学してきましたー
先日『里の曙』でお馴染みの町田酒造さんの工場見学に行ってきました
今まで工場の前は車で頻繁に往来していて
いつかは工場見学をしたいと思っていたのですが
今回ついに行く事ができました!

先ず始めに見学客は敷地内中央の建物でビデオ鑑賞をした後に
ガイドの方の誘導で焼酎造りをしている工場内部へ移動します。
基本的な黒糖焼酎製造の工程は前回の奄美大島酒造の蔵見学を
させていただいた際にこのブログに載せましたので
今回はガイドさんに説明してもらった
町田酒造さんの黒糖焼酎の特長を書きます。
町田酒造の黒糖焼酎の特長

町田酒造と言えば『里の曙』が有名ですが、
この里の曙は奄美にある酒造メーカーの中で
一番最初に『減圧蒸留』と言われる製法を取り入れた言わば
黒糖焼酎のパイオニア的銘柄です。
減圧で蒸留された黒糖焼酎は常圧で蒸留された焼酎と比べ
雑味が少なくスッキリとして飲みやすいのが特長です。
それまでの『焼酎=年配の男性が晩酌で飲むクセのある強いお酒』
という概念を覆し幅広い世代に支持され、その事で『減圧蒸留』製法は
その後の黒糖焼酎の新たなスタンダードになりました。

写真中央の設備が減圧蒸留タンクです。
ほぼ真空な為沸点が低く原料を約60度で沸騰させる事ができるそうです。
町田酒造では香り高く芳醇な黒糖焼酎に成るように
原料の黒糖を一般的な黒糖焼酎と比べて多く使用します。
また3次仕込みまで行うのも町田酒造の黒糖焼酎の特長です。
これは、使われる黒糖の量が多いことで、糖分を分解する際の菌の
負担を軽減するのが目的なんだそうです。

一回の仕込みでだいたい米2トンと黒糖を5トン使用します。
『キビを作らずして黒糖焼酎を語るなかれ』という
杜氏・長谷場洋一郎の言葉のもと、2017年からは
さとうきびの栽培も従業員の手によって行われているそうです。
巨大な貯蔵タンク

写真にある巨大なタンクにはタンク1つに付き里の曙の原酒が
なんと!36万リットルも貯蔵されているんだそうです!
これは1人の人が毎日1升(1・8ℓ)飲み続けても
548年かかる量です
環境
環境への配慮もしっかり行っていて
蒸留の工程が終わった蒸留粕は敷地内の専用プラントで焼却され炭となって
家畜の餌や植物の肥料として再利用されます。
工場内で使用した水は敷地内にある浄化設備を通じて環境基準をクリアするレベル
にまで浄化し綺麗にしてから排出されるんだそうです

今回見学させてもらった日は晴天で広い敷地内では従業員と思わしき
方々がちょうど中庭の花々の手入れ中で、とてものどかな感じがしました。
敷地内にはバナナやバンシロウ等の木も生えていて、個人的にそういった物も
見て回れる事も魅力の一つと思いました。
町田酒造工場見学
見学時間/ 約60分
時間帯/ 9:00~
10:00~
11:00~
13:00~
14:00~
15:00~
駐車場: 有り
参加人数の把握も有るので事前に予約をお願いしますとの事です
今まで工場の前は車で頻繁に往来していて
いつかは工場見学をしたいと思っていたのですが
今回ついに行く事ができました!

先ず始めに見学客は敷地内中央の建物でビデオ鑑賞をした後に
ガイドの方の誘導で焼酎造りをしている工場内部へ移動します。
基本的な黒糖焼酎製造の工程は前回の奄美大島酒造の蔵見学を
させていただいた際にこのブログに載せましたので
今回はガイドさんに説明してもらった
町田酒造さんの黒糖焼酎の特長を書きます。
町田酒造の黒糖焼酎の特長

町田酒造と言えば『里の曙』が有名ですが、
この里の曙は奄美にある酒造メーカーの中で
一番最初に『減圧蒸留』と言われる製法を取り入れた言わば
黒糖焼酎のパイオニア的銘柄です。
減圧で蒸留された黒糖焼酎は常圧で蒸留された焼酎と比べ
雑味が少なくスッキリとして飲みやすいのが特長です。
それまでの『焼酎=年配の男性が晩酌で飲むクセのある強いお酒』
という概念を覆し幅広い世代に支持され、その事で『減圧蒸留』製法は
その後の黒糖焼酎の新たなスタンダードになりました。
写真中央の設備が減圧蒸留タンクです。
ほぼ真空な為沸点が低く原料を約60度で沸騰させる事ができるそうです。
町田酒造では香り高く芳醇な黒糖焼酎に成るように
原料の黒糖を一般的な黒糖焼酎と比べて多く使用します。
また3次仕込みまで行うのも町田酒造の黒糖焼酎の特長です。
これは、使われる黒糖の量が多いことで、糖分を分解する際の菌の
負担を軽減するのが目的なんだそうです。
一回の仕込みでだいたい米2トンと黒糖を5トン使用します。
『キビを作らずして黒糖焼酎を語るなかれ』という
杜氏・長谷場洋一郎の言葉のもと、2017年からは
さとうきびの栽培も従業員の手によって行われているそうです。
巨大な貯蔵タンク
写真にある巨大なタンクにはタンク1つに付き里の曙の原酒が
なんと!36万リットルも貯蔵されているんだそうです!
これは1人の人が毎日1升(1・8ℓ)飲み続けても
548年かかる量です

環境
環境への配慮もしっかり行っていて
蒸留の工程が終わった蒸留粕は敷地内の専用プラントで焼却され炭となって
家畜の餌や植物の肥料として再利用されます。
工場内で使用した水は敷地内にある浄化設備を通じて環境基準をクリアするレベル
にまで浄化し綺麗にしてから排出されるんだそうです

今回見学させてもらった日は晴天で広い敷地内では従業員と思わしき
方々がちょうど中庭の花々の手入れ中で、とてものどかな感じがしました。
敷地内にはバナナやバンシロウ等の木も生えていて、個人的にそういった物も
見て回れる事も魅力の一つと思いました。
町田酒造工場見学
見学時間/ 約60分
時間帯/ 9:00~
10:00~
11:00~
13:00~
14:00~
15:00~
駐車場: 有り
参加人数の把握も有るので事前に予約をお願いしますとの事です
2018年01月23日
工場見学①
奄美大島酒造さんへ工場見学に行って来ました

まず敷地内の左側に在る建物内に居た女性の方に蔵見学しに来たことを伝えると
「工場見学ツアーの第一陣は午前10時で出発しましたよ」って言われ、その後
「案内する人はいないですが、一人で工場に入って見て回っても良いですよ」って
事だったので、一人で工場内を見て回る事に

洗米・蒸米
洗米・蒸米に麹菌をかけて35度~36度の温度で麹を仕上げる工程

1次仕込み
出来上がった麹はこのタンクで地下120mからくみ上げられる
「じょうごの天然水」と「酵母」と一緒に仕込まれます。
じょうご川の天然水は奄美で最も美味しいと言われているので、
奄美大島酒造さんも昭和57年に工場を
名瀬から現在の龍郷へ移転したそうです
参照URL↓↓↓
http://www.jougo.co.jp/kodawari.html
2次仕込み
原料を2次仕込みタンクに移し奄美大島産100%の黒糖を流し込みもろみを作ります
2週間ほどタンク内で発酵させその間黒糖の糖分がゆっくりとアルコールへと変ります
奄美大島産100%の黒糖で焼酎を仕込んでいる蔵元は奄美大島酒造さんだけだそうです

蒸留
2次仕込の終った原料を蒸留する為の蒸留器です。
蒸留器は2種類あり、常圧蒸留器のK1式蒸留器と常圧、減圧の河内式蒸留器です。
一般的に、減圧で蒸留された焼酎は、クセが少なくフルーティーで円やかな
味わいで、飲みやすい焼酎になります。じょうごがこの製法で造られた
黒糖焼酎になります。
また、常圧で蒸留された焼酎は、一般的に香りが高く独特なコクと旨みがあります。
高倉や浜千鳥乃詩等がこの製法で造られた黒糖焼酎です。
貯蔵
蒸留を終えた各黒糖焼酎は品質を安定させる為に
最低2年間はタンクで貯蔵されるそうです。
長く寝かせれば寝かせるほど、円やかになるのが奄美黒糖焼酎だそうです。
ビン詰め・出荷
貯蔵・熟成を終えた原酒は、25度・30度の製品として出荷する為に割り水を加え、
焼酎はビン詰めされ、検査を終えてラベルを張り、商品として出荷されます。
本当にピカピカで立派な工場でした
奄美大島酒造さん有難う御座いました!!
勝手に一人で回っただけですが・・・
今回行った時点では焼酎の製造はまだ始まっていませんでしたが
製造が始まると、工場内が黒糖の甘い香りで一杯になるから直ぐに分かる
そうです。そして1人でも工場見学できて結構勉強になったんですが、
事前に時間とかを下調べしていなかったが為に、ガイドの方に色々聴けなかったのが
本当に悔やまれます。
次回は焼酎製造期間内にまた来てみたいです。
工場見学ツアーの時間は
平日 10:00~ 14:00~ 16:00~
土日祝日の工場見学は電話にてご相談くださいとの事です
0997-62-3120
お得な情報も配信 『めぐみ通信@LINE』 も宜しくお願いします!

(有)ピーシーショップめぐみ
TEL 52-1327
駐車場 あり
営業時間 10:00-24:00
休み お盆、元日のみ
まず敷地内の左側に在る建物内に居た女性の方に蔵見学しに来たことを伝えると
「工場見学ツアーの第一陣は午前10時で出発しましたよ」って言われ、その後
「案内する人はいないですが、一人で工場に入って見て回っても良いですよ」って
事だったので、一人で工場内を見て回る事に
洗米・蒸米
洗米・蒸米に麹菌をかけて35度~36度の温度で麹を仕上げる工程
1次仕込み
出来上がった麹はこのタンクで地下120mからくみ上げられる
「じょうごの天然水」と「酵母」と一緒に仕込まれます。
じょうご川の天然水は奄美で最も美味しいと言われているので、
奄美大島酒造さんも昭和57年に工場を
名瀬から現在の龍郷へ移転したそうです
参照URL↓↓↓
http://www.jougo.co.jp/kodawari.html
2次仕込み
原料を2次仕込みタンクに移し奄美大島産100%の黒糖を流し込みもろみを作ります
2週間ほどタンク内で発酵させその間黒糖の糖分がゆっくりとアルコールへと変ります
奄美大島産100%の黒糖で焼酎を仕込んでいる蔵元は奄美大島酒造さんだけだそうです
蒸留
2次仕込の終った原料を蒸留する為の蒸留器です。
蒸留器は2種類あり、常圧蒸留器のK1式蒸留器と常圧、減圧の河内式蒸留器です。
一般的に、減圧で蒸留された焼酎は、クセが少なくフルーティーで円やかな
味わいで、飲みやすい焼酎になります。じょうごがこの製法で造られた
黒糖焼酎になります。
また、常圧で蒸留された焼酎は、一般的に香りが高く独特なコクと旨みがあります。
高倉や浜千鳥乃詩等がこの製法で造られた黒糖焼酎です。
貯蔵
蒸留を終えた各黒糖焼酎は品質を安定させる為に
最低2年間はタンクで貯蔵されるそうです。
長く寝かせれば寝かせるほど、円やかになるのが奄美黒糖焼酎だそうです。
ビン詰め・出荷
貯蔵・熟成を終えた原酒は、25度・30度の製品として出荷する為に割り水を加え、
焼酎はビン詰めされ、検査を終えてラベルを張り、商品として出荷されます。
本当にピカピカで立派な工場でした
奄美大島酒造さん有難う御座いました!!
勝手に一人で回っただけですが・・・
今回行った時点では焼酎の製造はまだ始まっていませんでしたが
製造が始まると、工場内が黒糖の甘い香りで一杯になるから直ぐに分かる
そうです。そして1人でも工場見学できて結構勉強になったんですが、
事前に時間とかを下調べしていなかったが為に、ガイドの方に色々聴けなかったのが
本当に悔やまれます。
次回は焼酎製造期間内にまた来てみたいです。
工場見学ツアーの時間は
平日 10:00~ 14:00~ 16:00~
土日祝日の工場見学は電話にてご相談くださいとの事です
0997-62-3120
お得な情報も配信 『めぐみ通信@LINE』 も宜しくお願いします!

(有)ピーシーショップめぐみ
TEL 52-1327
駐車場 あり
営業時間 10:00-24:00
休み お盆、元日のみ